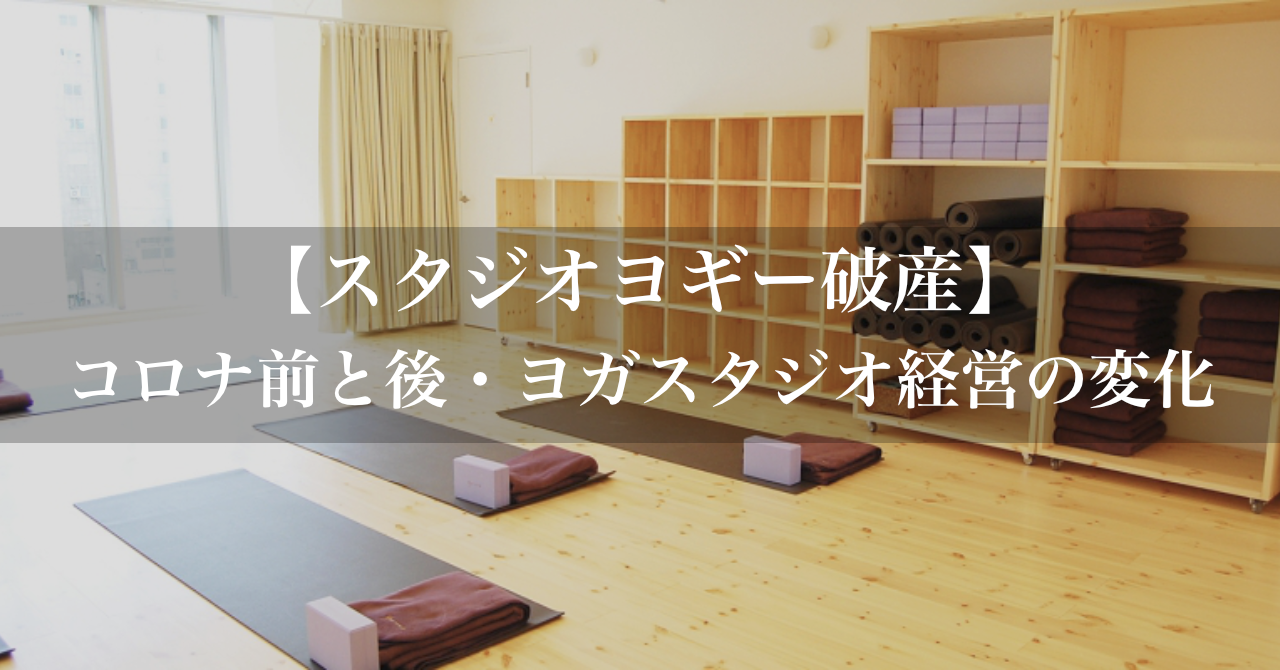先日、大きなニュースが飛び込んできました。
「スタジオヨギーが破産申請」。
Yahoo News| ヨガスタジオとしては過去最大の倒産 ヨガ・ピラティス教室運営の(株)ヨギー(東京)が破産
2004年の創業以来、全国に10店舗以上を展開してきたスタジオヨギーは、日本における都会型ヨガスタジオの先駆けであり、ヨガ業界の象徴的な存在でもありました。
そのスタジオが2025年8月1日付で東京地裁に破産を申請。負債総額はおよそ6億2000万円と報じられています。
ヨガに携わる人間として、このニュースは本当にショックでした。
私自身、日比谷・銀座・中目黒・新宿・池袋・横浜など、主要なスタジオに足を運んだことがあります。どこも駅から近く、洗練された内装で、清潔感があり、まさに「ヨガを都会的に楽しめる空間」でした。
ヨガスタジオ業界において、ヨギーは「お手本」でもあったのです。

スタジオヨギーが持っていた存在感
ヨガスタジオというと、以前は小さなカルチャースクール的な存在が多く、「通いやすい場所で、少人数で習う」という形が一般的でした。
そんな中、スタジオヨギーは都会の一等地に複数の大型店舗を構え、ヨガだけでなくピラティスやボディワークもラインナップ。カフェやアパレルと並ぶような「ライフスタイルの一部」としてヨガを打ち出した点が革新的でした。
スタジオヨギーの登場によって、ヨガが「おしゃれで都会的なもの」として定着したといっても過言ではありません。
それだけに今回の破産は、「あのヨギーでさえ持たなかったのか…」という衝撃を与えています。

ヨガスタジオ経営の収支構造
ここで少しリアルな話をします。
ヨガスタジオを経営したことがある方なら分かると思いますが、このビジネスモデルは最初から利益を出しにくい構造になっています。
- 駅近でアクセスが良いことが必須
- 一定以上の広さが必要(小さすぎると採算が取れない)
- 集客できる時間帯は限られる(平日夜や週末午前が中心)
つまり「稼げる時間帯は限られているのに、固定費は常に発生する」仕組みなんです。
実際、スタジオの大きなコストは次の2つ。
- スタジオ家賃(しかも一等地なら数百万円単位)
- 人件費(受付スタッフ、インストラクター、清掃など)
これに広告費や設備維持費が加わると、月間で数千万円規模のランニングコストになることも珍しくありません。
一方で収入の柱は、ほぼチケット収入や月会費。
つまり「限られた時間に、限られた人数しか受け入れられない」構造なので、黒字化が非常に難しいのです。
今回報じられた負債総額6億2000万円の多くも、家賃負担が大きかったのではないかと想像します。

コロナ禍とその後遺症
破産の直接の原因として、多くの人が思い浮かべるのはコロナ禍です。
2020年以降、ヨガスタジオは営業制限を強いられ、オンライン化を迫られました。
スタジオヨギーもオンラインクラスを展開し、その事業は現在も別会社で続いています。
しかし問題は、「リアル店舗を維持しながらオンラインに移行する」難しさです。
- オンラインでは安価なサービスが増えた
- そもそも「リアルクラス離れ」が加速した
- でも店舗の家賃や人件費は消えない
この三重苦を抱えた状態で、体力のある大手ほど負担が大きくなったのではないかと思います。

大手ならではのリスク
多店舗展開はブランド力を生みますが、同時に大きなリスクも背負います。
- 店舗ごとの収益格差
- 人材の確保と教育コスト
- 広告宣伝費の肥大化
- 経営の意思決定が遅れる
小規模スタジオなら「お客さんの声を直接聞いてすぐ改善」できますが、大手はそうはいきません。
加えて、近年はフィットネスジムや低価格なオンラインサービスとの競争が激化。結果的に「大手であること」が経営の足かせになった可能性は高いです。
養成スクール事業の変化
もう一つ大きな要因として考えられるのが、ヨガインストラクター養成事業の不振です。
特にYMCはスタジオを持たず、養成スクールが事業の柱でしたが、2024年に撤退しました。

背景には、オンラインRYT200(ヨガアライアンスの資格)が爆発的に増えたことがあります。
コロナ禍で「自宅から格安でRYT200が取れる」ようになり、対面スクールの受講者が大幅に減少しました。
養成スクールの売上は、年間で数千万円規模の減収になっていたと推測されます。
ヨガスタジオ自体は、クラスチケット代金からのみでは、家賃を払うので精一杯。利益を生みにくいため、養成スクールで売上をたてているスタジオの場合、経営上、大打撃を受けます。

小さなスタジオの強みとこれからの生き残り戦略
ここまで読むと「ヨガスタジオ経営は不可能なのでは?」と思われるかもしれません。
確かに、大手の多店舗展開は時代に合わなくなってきていると思います。
でも、小規模スタジオには小規模ならではの強みもあります。
- 家賃を抑えられる
一等地でなくても、地域に根ざしたスタジオなら成立する。 - インストラクターと生徒の距離が近い
信頼関係があると、長く通ってもらえる。 - フレキシブルに対応できる
オンラインとリアルのハイブリッドも、規模が小さい方が素早く導入できる。 - 固定費を下げやすい
受付を置かない、予約システムを自動化するなど、省コストの工夫が可能。
つまり「大きく儲ける」のは難しくても、「持続可能な形で続ける」ことは十分にできるのです。
まとめ:これからどうしてく?
スタジオヨギーの破産は、ヨガ業界にとって一つの時代の終わりを告げる出来事でした。
でも同時に、「これからどうやってヨガを伝えていくのか?」を考えるきっかけにもなるはずです。
スタジオ経営は、華やかに見えて実は常に不安定。
私自身も日々、悩みや不安を抱えながら運営しています。
ただ、それでも「小さなスタジオだからできること」がある。
「今の時代に合ったヨガの伝え方」がある。
そのことを忘れずに、一歩ずつ前に進んでいきたいと思います。
👉 あなたは、このニュースをどう感じましたか?
👉 もし通っていたスタジオがなくなったら、どんな形でヨガを続けたいですか?